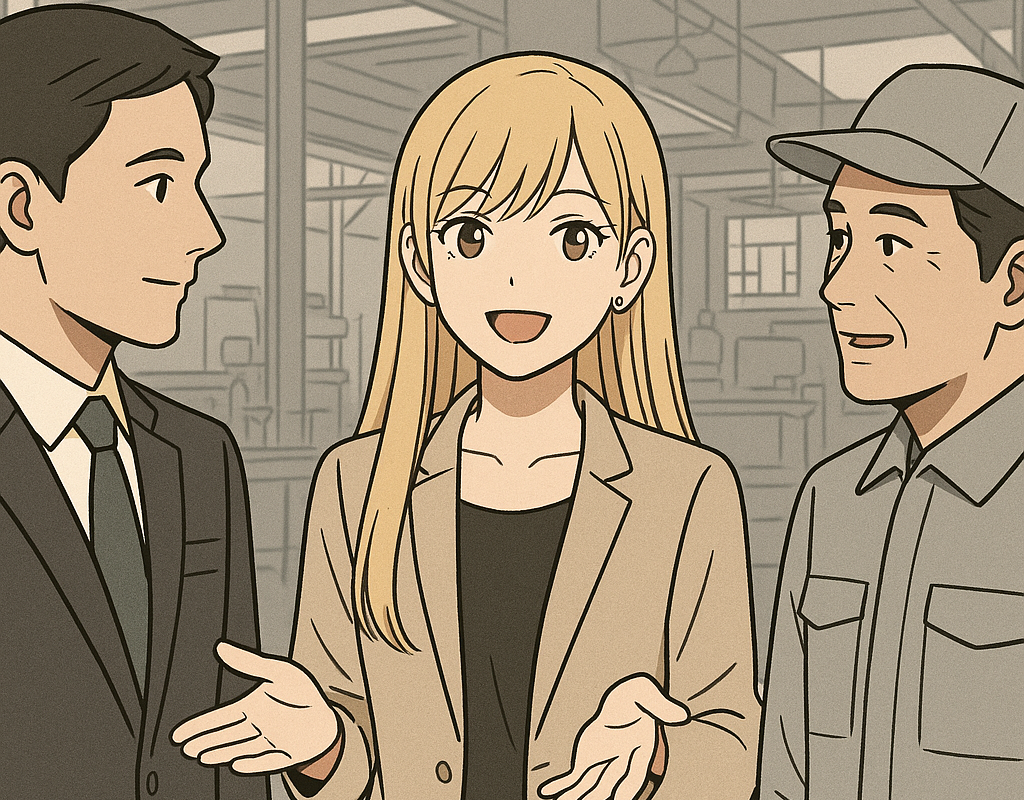信頼を積み重ねた先に、本当に良い商品は生まれる
1. 現場を知らないと、良い商品は作れない
モノづくりは一回限りの仕事じゃない。企画して、作って、納めて終わり――そんな単発のやり取りで良い商品が生まれることなんてほとんどない。大事なのは、仕事を重ねていく中でお互いの考え方や特性を理解し、阿吽の呼吸で動けるようになることだと思う。
でも現場にいると正直、「なんでこんな指示が飛んでくるんだろう」と感じることは少なくない。素材や工程を知らないまま無理な依頼をされると、工場の人間は困惑するし、不満が心の中に積もる。もちろんそんなことは口には出さない。けれど、もし自分の友人がこれからモノづくりに携わるなら、工場にそう思われる立場になってほしくない。
だからこそ声を大にして伝えたいのは、「現場を一度見てみろ」ということ。図面やパソコンの前で考えるだけでは、絶対に気づけないことがある。その工場の得意分野やクセ、工程ごとの手間や制約――そういうものを肌で感じて初めて、リアルな想像力が働く。
2. 発注者は“伝書鳩”じゃない
工場に発注する人にも、それぞれの仕事がある。マーケティング、デザイン、ライセンス元との交渉、販売先とのやり取り…。どれも大事な役割だ。
でも「自分の仕事はそこだけ」と思っていたら、先はない。
ただお客さんの言葉をそのまま工場に伝えるだけの“伝書鳩”では、モノづくりは前に進まない。大事なのは、工場の考え方とお客さんの考え方の両方を理解し、そのうえで良い落とし所を見つけることだ。
どちらかに偏りすぎてもダメだ。お客さんに同調しすぎて、工場を責めるだけの人もいるけれど、それは最悪のパターン。逆に工場の都合ばかり優先すれば、商品は売れない。
お客さんから相談を受けたときには、自分なりに考えることも必要だ。でも製造については工場の方がはるかに詳しい。だからこそ、工場に相談することは必須だ。工場への相談なしにお客さんと勝手に決めてしまえば、ほぼ確実に上手くいかない。
根底にあるのは、モノづくりそのものへのリスペクトだと思う。お客さんにも、工場にも、そして自分の役割にも敬意を持てるかどうか。それが最終的な成果を分ける。
3. 信頼の積み重ねが質を高める
結局、良いモノづくりって「立場を超えて考えられるかどうか」に尽きる。最初の仕事では探り探りでも、二度三度と重ねるうちに「ここは任せても大丈夫」「これなら提案できる」っていう信頼が生まれる。その関係性こそが、モノづくりの質を底上げしていく。
だから、これからモノづくりに関わる人に伝えたい。机上の空論に走る前に、一度でいいから現場に足を運んでほしい。音楽を聴かずに楽器を設計できないように、現場を知らずに商品を企画することはできない。
モノづくりは、立場を越えた信頼の積み重ね。お互いに歩み寄り、阿吽の呼吸で進められるようになったとき、はじめて「本当に良い商品」が形になるんだよ。たぶん。しらんけど。